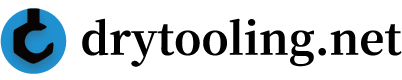ドライツーリング(drytooling)とは?
ドライツーリングとは、岩稜帯または人工壁において、アイスアックスとクランポンを用いて登るスタイルのクライミングです。ドラツーと略すこともあります。
氷瀑を登攀対象にするアイスクライミングから発展した形で、氷と岩が入り混じるルートを登攀対象にするミックスクライミングというジャンルがあります。
ドライツーリングはさらに発展した形で、岩の部分のみにフォーカスした登攀スタイルであり、ルート上の強点をついて登ります。
道具を用いるという意味でエイドクライミングとも言えますが、人工壁やボルトの打たれたスポートルートもあり、フリークライミングとしての一面も持ち合わせます。

強傾斜の岩壁でのドライツーリング 
人口壁でのドライツーリング練習

また、岩・氷・雪が混じる冬期アルパインクライミングにおいて、 岩の剥き出した部分を手を使わずにアイスアックスとクランポンで登ることをドライツーリングと呼ぶこともあり、スポーツクライミングとしてのドライツーリングは日本ではまだまだ認知度は低いと言えます。
ドライツーリングは広義では、ミックスクライミングの一種とも言えますが、氷瀑を必要としないため、季節を問わず一年を通して楽しむことができます。そのため、アイスクライミングやアルパインクライミングのオフシーズンの練習としてもドライツーリングは度々行われます。


北海道の神居古潭や宮城県の二口峡谷など、日本にもミックスクライミングができるゲレンデがいくつかあります。 多くの場合、ミックスクライミングのルートは、冬期以外の3シーズンにおいてはそのままドライツーリングのルートとして登られています。
また、宮城県の鎌倉山など、純粋なドライツーリングのルートが開拓されているゲレンデもありますが、公開されているエリアは非常に限られています。

神居古潭 
鎌倉山
ミックスクライミングでは、ルートのグレード表記を「Mグレード」で表します。北海道神居古潭の「斬鉄剣」がM11+となっており、日本の難関ルートとして有名です。対して、ドライツーリングでは「Dグレード」で表します。宮城県二口峡谷の「鳥獣戯画」が推定D13と言われており、ドライツーリングルートとしては国内最難関との呼び声が高いです。
グレード表記の詳細は以下の記事で紹介しています。
競技としてのアイスクライミング
国内外でドライツーリングは競技としても行われており、少々わかりづらいですが、アイスクライミングのコンペと銘打って開催されることが多いです。
アイスクライミングのコンペでは、実際の氷がルート全体を占めるわけではなく、アイスアックスをフッキングするための人工ホールドやクランポンを蹴り込むためのコンパネが使われることがほとんどです。
また、マグロと呼ばれる木材や金属のチェーン等、パターンの富んだオブジェクトがよく吊るされ、フィギュア4・フィギュア9のムーブを頻繁に使うことが特長です。
アイスクライミングのコンペの競技内容は実質的にドライツーリングとなっており、UIAAアイスクライミングワールドカップにおいても、これは同じです。
アルパインのシーンではあり得ないような傾斜やアクロバティックなムーブが求められることもあり、ドライツーリング特有の技術が試されます。


アイスホールドへの打ち込み(昭島ドライツーリングコンペ) 
Ouray Ice Festival 2018 ミックスクライミングリードコンペの様子(アメリカコロラド州)

進化するドライツーリングギア
近年、登攀用具の発展も目覚ましく、これまでアルパイン、アイスクライミングのシーンで使われてきたギアに比べ、よりコンペ仕様に特化した先鋭的なアックスやピック、アイゼン一体型のブーツ(=フルートブーツ)が登場しています。高難度の課題を求める競技志向の選手の間では、これらの装備が標準になりつつあります。

ドライツーリング(drytooling)は、toolという名の通り、道具によって有利不利に大きく差がつくことがあります。道具を知り、自分にとって最適なチューニングを施すことも重要になります。
しかしながら日本では、未だにこれらのギアの入手難易度が高く、練習環境も限られているため、スポーツクライミングのジャンルとしては非常にマイノリティーな存在となっています。
本サイトでは、そんなドライツーリングの魅力をひとつでも多く紹介できればと思っています。
日本ドライツーリング史年表
2022年
2022年9月
宮城県・二口峡谷・風の堂エリア「天地明察(D14-〜D14?)」中島正人、開拓初登
2022年8月
中島正人がスイス・エプティンゲン「IronKnight(D14+/D15-)」をRP。日本人のDグレード記録を更新。
竹内春子がスイス・エプティンゲン「Ironman(D14+)」をRP。日本人女性のDグレード記録を更新。
2022年5月
宮城県・二口峡谷・風の堂エリア「鳥獣戯画(D13)」竹内春子、第3登。女性として初登。日本人女性としては最高グレード更新。
宮城県・ハンギングガーデン「魂の萌芽(D9)」橋本翼、初登。

埼玉県・中津川アイスロード・奈落エリア「児雷也(D9)」橋本翼、開拓初登

2022年3月
ベータクライミングジム(東京)にて「カイラス・ベータ ドライツーリングカップ2022」が開催。オープンクラスで中島正人が優勝。メインルートセッターは竹内春子。

2022年2月
UIAAアイスクライミング世界選手権(スイス・ザースフェー)にて、竹内春子が女子リード部門で決勝進出、7位となった。
UIAAアイスクライミング北米選手権(アメリカ・オウレイ)にて、女子リード部門で竹内春子が準優勝、笹川淳子が7位。竹内春子はアイスクライミング国際大会での日本人最高順位を更新。
2021年
2021年10月
宮城県・二口峡谷・風の堂エリア「鳥獣戯画(D13)」賀門尚士、第2登(わずか2トライでの完登)
2021年7月
宮城県・二口峡谷・風の堂エリア「鳥獣戯画(D13)」中島正人、開拓初登
2021年3月
ベータクライミングジム(東京)にて「モンチュラ・ベータ ドライツーリングカップ2021」が開催。オープンクラスで松永英知が優勝。メインルートセッターは竹内春子。
埼玉県・中津川アイスロード・奈落エリア「業(カルマ)(M9)」橋本翼、開拓初登
2020年
2020年10月
宮城県・二口峡谷・風の堂エリア「神楽(D9)」中島正人、初登
2020年3月
岩根山荘(長野県川上村)にて開催予定だった「モンチュラ・ドライツーリングチャンピオンシップ2020」がコロナウィルス流行のため中止。
2020年1月
UIAAアイスクライミングワールドカップ(中国・長春)にて、日本人過去最多(男子5名、女子6名)の出場。女子選手は全員準決勝進出の快挙。さらに竹内春子が日本人女子選手として10年ぶりに決勝進出を果たし、7位となった。
UIAAアイスクライミングワールドカップ(韓国・チョンソン)にて、小武芽生が決勝進出、7位となった。また今大会はアジア選手権を兼ねており、アジア3位に入賞した。
2019年
2019年5月
宮城県・二口峡谷・風の堂エリア「電撃グルーヴ(D8)」千葉英一、開拓初登
2019年3月
岩根山荘(長野県川上村)にて「モンチュラ・ドライツーリングチャンピオンシップ2019」が開催。男子リード部門で橋本翼が優勝。男子スピード部門で松永英知が優勝。女子リード部門および女子スピード部門で竹内春子が優勝。メインルートセッターはKwon Young Hye。
UIAAアイスクライミングワールドカップ(アメリカ・デンバー)にて、門田ギハードが日本人男子選手では8年ぶりに決勝進出を果たし、8位となった。
2018年
2018年10月
韓国よりKwon Young Hyeが初来日。長野県Zig’s Rockにて、日本で最初の「Kwon’s Drytooling Academy」が開催。
Kwon Young Hye日本滞在時での主な登攀記録は以下の通り。
- 宮城県・二口峡谷・風の堂エリア「暴君(M10)」OS(※尚、この際「暴君」はDグレードでD11+との判定あり。)
- 「狗鷲夏ルート(D9)」OS
- 宮城県・鎌倉山「はやぶさ(D11)」OS
- 「はやて(D10)」OS
- 「MAXやまびこ(D9+)」OS
2018年7月
SNSを介してのKwon Young Hyeの呼びかけで、日本から6名の選手が韓国開催のKwon’s Drytooling Academyに参加。
※この頃より、強豪国である韓国との交流が活発となり、日本にも高度なテクニックやノウハウが伝授され、競技用アイスアックスOctaが輸入される。
2018年6月
ベータクライミングジムにて、ドライツーリングウォールがオープン。一般利用はできず、毎月セッションのイベントが開催。
2018年5月
スイス・エプティンゲン「アイアンマン(D14+)」賀門尚士、RP。
2018年5月
宮城県・二口峡谷・風の堂エリア「暴君(M10)」中島正人、第3登。ドライツーリングルートとして初登。
2018年2月
岩根山荘(長野県川上村)にて「モンチュラ・ナナーズカップ2018」が開催。男子オープンクラスで嶋田豊が優勝。女子オープンクラスで石原幸江が優勝。メインルートセッターは中島正人。
2017年
2017年10月
岩根山荘(長野県川上村)の室内ジム「オンサイト」にて「第2回岩根カップ」が開催。全選手オープン参加で、アメリカから参戦したKevin Lindlauが優勝。メインルートセッターは嶋田豊。
2017年7月
岩根山荘(長野県川上村)の室内ジム「オンサイト」にドライツーリングウォールが新設オープン。同日、「第1回岩根カップ」が開催。全選手オープン参加で、嶋田豊が優勝。メインルートセッターは中島正人。
2017年4月
モリパークアウトドアヴィレッジ(東京・昭島)にて「スピードスターズ2018」が開催。その余興で新設されたドライツーリングウォールがお披露目され、奈良誠之、吉田貢、八木名恵によるデモンストレーションが開催。
2017年3月
岩根山荘(長野県川上村)にて「モンチュラカップ2017」が開催。男子オープンクラスで森田啓太が優勝。女子オープンクラスで八木名恵が優勝。メインルートセッターは中島正人。